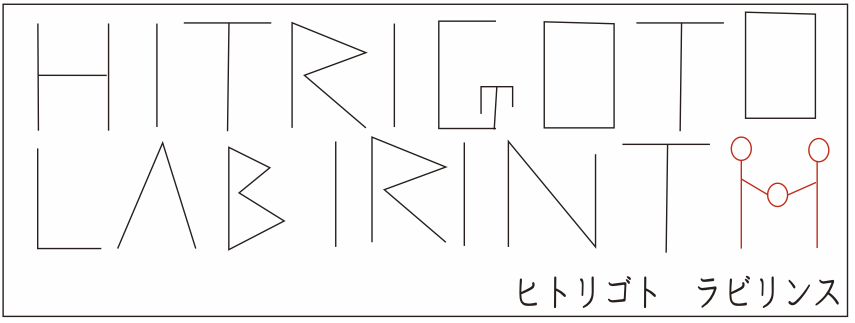2015年の『ケンとカズ』で注目を浴びた小路紘史監督が、なんと8年の時間をおいて打ち出すジャパニーズ・ノワール。弟を亡くした死体解体のプロ、辰巳を遠藤雄弥。そのバディとなっていく葵を森田想が演じる。第36回東京国際映画祭「アジアの未来」部門出品作品。
目次
- 鑑賞後の短評
- あらすじ
- とにかくパワーに溢れた、新しい時代の日本製ノワール
- ただパワフルなだけではない、繊細な映画
- 小路紘史監督の演出がとにかく良質
- 暴力的なジャンル映画でありながら、現代の閉塞感を射抜く叙情的な映画でもある
鑑賞後の短評
あらすじ
裏家業に生きる男辰巳(演:遠藤雄弥)は、麻薬中毒になった弟と死別する。それ以降、死体解体人として信頼を得ていくが、元恋人である京子(演:龜田七海)と再会し、その妹・葵(演:本多想)の面倒を見てほしいと頼まれる。葵に振り回されながらも京子の頼みと受け入れる彼。だが、その京子の殺害現場に遭遇したことで、事態は一変。なんとか事態を収めようと奔走する辰巳を尻目に、葵は姉の復讐を始めてしまい…。複雑に絡み合った運命は、二人の心を変えていく。
とにかくパワーに溢れた、新しい時代の日本製ノワール
『太陽を盗んだ男』『狂った野獣』70年代から80年代に至るまでの日本製ノワールは本当にパワーに満ち溢れていて、そのパワーのようなものはなんとなく失われてしまったと思っていた。『辰巳』を見るまでは。本作の魅力は映画が発散する圧倒的なパワーだ。たとえば、キャラクターたちの掛け合いはほぼ暴言の言い合いで、片方が強い力で怒鳴れば受ける方もさらに強い力で返す。そのグルーヴの高まりが、映画に圧倒的なパワーを与ていく。主人公辰巳役の遠藤雄弥はインタビューにて、「例え話」と笑いながら前置きした上で「現場にはケンカの強い役者しかいない」と語った。実力やキャリアに秀でた猛者どもの中に入り込んでいくのには相当なエネルギーを必要としたことだろう。他の役者に負けまいと躍動する遠藤雄弥のパワーが、辰巳というキャラクターが持つエネルギッシュな魅力を体現している。そして何より、役者たちが皆生き生きと芝居をしているのがスクリーンのこちら側にも伝わってくるのだ。これ以上の悦びはない。
ただパワフルなだけではない、繊細な映画
今作は80年代から70年代のパワフルな映画の雰囲気を存分に匂わせながら、同時に今の邦画らしい繊細さを讃えた作品でもある。これも辰巳を演じた遠藤雄弥の力が大きい。裏世界の暴力が支配する空間において、強い言葉を使っても隠せない繊細さが辰巳というキャラクターから漏れ出しているのだ。それもそのはず、彼は弟を亡くした哀しみと助けられなかったという引け目、何より優しさを持ち合わせたキャラクターなのだ。この複雑さが『辰巳』という映画をさらに魅力的なものにしている。
葵との関係性の中で
彼のパーソナリティを深掘る上で欠かせないのが、行動を共にする葵の存在だ。『レオン』におけるマチルダ的な存在でもある葵だが、彼女は誰かの下について教えを乞うという人間では全くない。言葉を選ばずに言えば本当に生意気なキャラクターだ。だが、彼女が他キャラクターと全く違うのは裏世界に全く力が及ばない点だろう。葵は他者を強い言葉で威圧するが、力を持たない彼女がするそれはただ去勢を張っているに過ぎない。だが同時に、裏社会の外側にいる彼女は辰巳が言われたくないと思っていることを的確に射抜く。葵と辰巳の初対面のシーンで、印象的な演出がある。京子の紹介で出会った二人はいきなり言い合いになり、葵は辰巳に唾を吐きかけるのだが。その唾が、辰巳の目から流れる涙のように映るのだ。葵はまさしく、辰巳が生きていく上で封印せざるを得なかった「涙」を象徴する存在なのだろう。力を持っているが心を閉ざした男・辰巳と心を持っているが力を持たない少女・葵は必然的に惹かれあったと言えるのだ。
『ドライヴ・マイ・カー』との相似点
その関係性の変化が『ドライヴ・マイ・カー』にも似た叙情的感覚で語られるのも、本作の魅力だ。というのも、辰巳が葵を車のどこに載せるかという部分に注意して見ると、言外に現れる関係性の変化を追うことができる。今作では、(終盤のとあるワンシーンを除いて)言葉は本音を語らない。言葉は強く、去勢を張らないと生きて生きない世界の話だからだ。だから、辰巳や葵の感情や心理の変化は映画的な画面の演出によって語られるのだ。たとえば「エンジンがかかりづらい車」という演出。これはサスペンス的な盛り上がりを作るための要素であると同時に、主人公辰巳の心理を反映したものであると思うのだ。中盤にある「エンジンはかかるが、葵をおいて車を発進させることはできない」という演出も胸に迫る。そしてそのエンジンを治すのは誰かというところも、辰巳の心理変化のキーとなっているのではないだろうか。
二人がそれぞれから影響を受け合って…
映画後半にかけて、葵と辰巳は互いに影響を与え合う存在となっていく。葵は辰巳から「力」とその使い方を学び、辰巳は葵との関係を通し自身の「心」と向き合っていくのだ。死んだように生きていた男、辰巳は始めて自分がしたいように生きれたし。葵も力を手に入れたことで始めて辰巳が抱えていた心理がどれだけ修羅の道を征くものだったかを痛感する。ラスト、葵は辰巳から「ある物」を受け継ぐのだが。ここで継承が起こるというのが、なんとも哀しく、同時にエモーショナルな帰結だ(辰巳を真にを理解できた時には、彼はもういないという)。
小路紘史監督の演出がとにかく良質
上記のように、周辺の要素全てが映画的に結びつき。映画が持つエモーションやエネルギーを損なうことなくキャラクターの心理を「説明」する演出は。小路監督の手腕あってのものだろう。小路監督の理念は、個々の演出に囚われない形でも発揮される。監督は本作における舞台を「日本的なものを排した、無国籍な空間」であると語っている。そうでなくては、もはやノワールは成立しないのだと。確かに、画面を見てみると日本的なものを想起させるような要素は極力映さないようになっているのがわかる。その画面を成立させるために、ロケーションにもとにかくこだわったそうだ。前作から8年という時間をかけたのも、細部に至るまでの作り込みが映画にとって必要だったからである。その覚悟と作り込みは、クオリティという形で画面に現れる。本作が他に類を見ない良質なエンタメでありながら、自主制作というスタイルにこだわった理由は映画のコントロール権を自分で持ちたかったからだという。自主制作というスタイルだからこそ、この徹底した画面コントロールと役者の魅力を引き出すことができたのだろう。
暴力的なジャンル映画でありながら、現代の閉塞感を射抜く叙情的な映画でもある
私は近年の邦画の潮流として「世界から拒絶された孤独な魂が、それでも実存を保つべく惹かれ合う二人」という映画が多い気がする(私は勝手に「実存のための他者」ものと呼んでいる)。『ドライヴ・マイ・カー』に始まり、『あのこは貴族』『ベイビーわるきゅーれ』『のぼる小寺さん』『正欲』『夜明けのすべて』…作品を列挙すると枚挙にいとまがないが。本作もこういった作品群に併せて語れる一本だと思う。本作は「終盤にいくにつれウェットになっていく展開に退屈さを感じた」という感想もあるが、辰巳という人間が自身のパーソナリティと向き合うというテーマもある以上、私個人としては必要なウェットさだったように思う。私は本作を、自身に変化をもたらしてくれる他者との関係を通じ再び実存を取り戻す話であると思っている。終盤に向けて葵と辰巳の関係が深く書き込まれるのも納得だった。