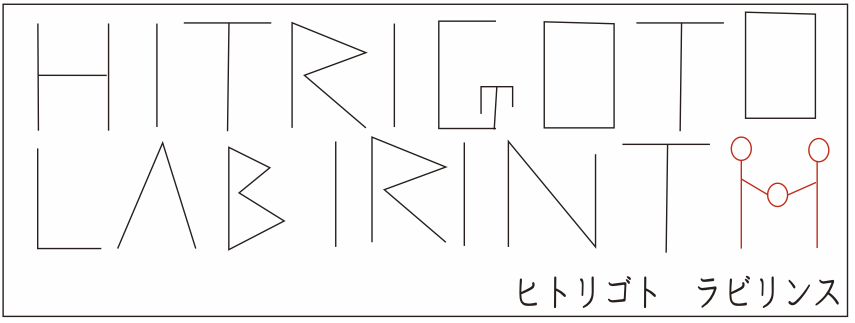『ドラえもん』『エスパー真美』『T・Pぼん』児童向けSFの傑作を数々生み出し続けた。藤子F不二雄としても知られる漫画家・藤本弘。そのイメージとは裏腹に実は毒っけの強い作品を数多く執筆しているのはご存じだろうか。今日はそんな藤子不二雄のダークな側面に迫る作品を紹介していこうと思う。
目次
「ダーク藤子不二雄」との出会い
私が初めて「ダーク藤子不二雄」とも言える存在と出会ったのは、短編集『平和を我らに 漫画が語る戦争』を読んだ時のことだった。水木しげる、手塚治虫、石ノ森章太郎といった錚々たる面子の中に、やはり藤子F不二雄の名前があったのだ。私は訝しんだ。藤子F不二雄さんは、そのほかの方々に比べ明確に戦争を描いているという印象がなかったからだ。もちろん『ドラえもん』の中に反戦テーマの会があったのも認識していたが、少なくとも私のその当時の印象は「明るい少年向け漫画」という印象がどうしてもあった。どちらかというとダークなイメージがあるのは藤子A不二雄さんの方、そういう印象を持っていたのは私だけではないだろう。
超兵器ガ一號
だが、私のそんな認識はたやすく覆ることになる。収録作品『超兵器ガ一號』を読んだからだ。この作品は収録されている他の作品とは全く違った形で戦争という事象を射抜いてみせる。
あらすじ
第二次世界大戦終盤、段々と不利になり押されていく日本。だがそんな日本のある島に一人の巨人が降り立つ。ポリネシア語の解読を得意とする海堂少尉の活躍もあって、巨人とのコミュニケーションを可能にした日本軍。自身をガリバーと自称することから「ガ一號」と名付けられた巨人は、なんと大東亜共和圏の理想に共鳴し日本軍とともに戦い始める。ガ一號の尽力もあって「正しい歴史」では起こるべき事象は回避され、日本は戦争に勝利するが…上記のあらすじにもあるように、本作は「もし第二次世界大戦敗北直前の日本に、巨人が味方したら」という架空戦記SFである。宇宙からやってきたガ一號は、優秀な技術力とその巨大な体躯でもって日本を勝利に導く。だがもちろん「あの戦争に勝利したヤッター」という物語を藤子不二雄が描きたい訳ではない。今作のメッセージは勝利した後にこそあるのだ。日本軍がガ一號に向ける敵意、人間の、そして戦争のくだらなさがこれでもかと出たシークエンスだ。そして今作の一番の肝は、なんといっても大オチ、漫画のラストカットだ。今作はラストに至るまでずっと「巨人が出てくる」ということ以外はリアリティラインが高く設定されていた。だからこそこのラストの「梯子を外された」感覚は唯一無二のものであろうし。恐ろしさ、悲しさ、面白さ、笑い、その全てがないまぜになった複雑な感慨に浸らせてくれる、無二のエモーションを生み出すシニカルな一作だったのだ。
ブラックなFとの邂逅
それからというもの、私は藤子F不二雄が描くブラックでシニカルな作品群に段々と惹かれていった。『ドラえもん』の人という認識だった藤子F不二雄を、初めて作家として意識した瞬間だった。同じ棚にあった『SF奇想短編集』を浴びるように読んだのを思い出す。藤子F不二雄作品を読み始めて何より驚いたのが『エスパー真美』が持つバランス感覚のシャープさだ。『SF奇想短編集』的なシニカルさダークさを残しながら、子ども向け作品としてチューニングされた完璧なバランスに驚愕したのだ。
おすすめの短編
そんな中でも、私が特に気に入っている作品を。何作か取り上げて紹介してみたいと思う。
オヤジ・ロック
この作品は、時間は絶対的か相対的かという。とても難しいテーマを扱っている一作だ。といっても、作品自体が難解ということは全くない。オヤジ・ロックという石を売らねばならないセールスマンの元に、一定の時間を巻き戻せるベルトを持った別のセールスマンが現れ、そのベルトを使ってオヤジ・ロックを売り付けていくというドタバタコメディ。だが最後にはSF的、哲学的な作品に仕上げてしまうのだから。やはり巨匠は偉大だ。このシニカルなオチは、ぜひ読んで体感してほしい。
ミノタウロスの皿
藤子F不二雄のブラックユーモア短編といえば本作が思い浮かぶ人も多いだろうと思う。それほどに有名で、同時に完成度の高い一作である。本作は食物連鎖をテーマとしており、牛が人間を食べるという星が舞台だ。そんな星に不時着した主人公の男は、食用種として牛に食べられるという「栄誉」を得た少女・ミノアと出会う。ミノアは牛に食べられるということを心から喜んでおり、主人公がいくら説得しようともその気持ちは変わらない。最終的にミノアは「ミノタウロスの皿」として牛に食される訳だが、何より最高なのはラスト一コマのオチに当たる部分だ。ミノアの運命を目にしてもなお、人間は食物連鎖の一部から自由になれないという皮肉を込めた、でも少し笑えるようなオチ。これこそが本作の真髄に当たるのだ。
劇画・オバQ
『劇画・オバQ』は、希望に満ちた少年向け漫画と皮肉とブラックユーモアに溢れた大人向け漫画。どちらも書くことができる藤子F不二雄だからこそ描けた作品だ。ストーリーは単純。大人になりサラリーマンになった「正ちゃん」の元にオバQが戻ってくるというお話。だが画風も含めリアリティラインが高く設定された本作において、オバQの存在は純然たる「違和感」でしかない。そんな世界の中で、オバQの登場人物たちが自身の持つ「オトナ性」「コドモ性」と向き合っていくのが本作のテーマだ。大人でも子どもでもない自分にとって、染み入る一遍だった。
藤子F不二雄は相対化の人だ
藤子F不二雄の魅力は、なんといっても相対化にあるのではないだろうか。自信がもつキャラクター漫画家としての才能を活かし、現実にある事象を全く別の形に読み替えてしまう。『ミノタウロスの皿』なんかはそういった特性が一番出た作品となっているのではないだろうか。人間と家畜という地球上に存在する構造を反転させ、持ち前のポップな画風でその反転に感情移入させる。そして、ラスト1コマで今私たちが生きる「現実」に引き戻させるのだ。こういった清濁併せ呑んだ人格があればこそ『ドラえもん』のような傑作少年漫画を描くことができたのだ。『ドラえもん』の根底には「現実は恐ろしいかもしれないが、それでも夢を見る」という考え方が大きく反映されている。