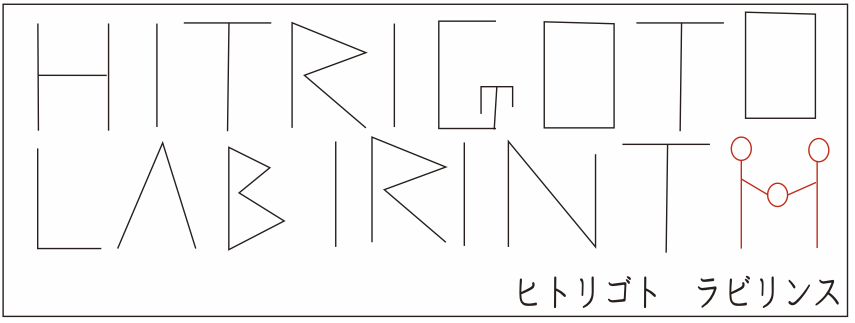乃木坂46一期生の高山一実の小説を『ぼっち・ざ・ろっく』『あの着せ替え人形は恋をする』等で有名なスタジオ「cloverworks」がアニメ化。主演の東ゆうを『逃げ上手の若君様』主演に抜擢された結川あさきが演じる。監督は篠原正寛、脚本を柿原優子が努める。
目次
- 鑑賞後の短評
- あらすじ
- これからするのは映画批評ではなく…
- 東ゆうは共感できない主人公か?
- 東ゆうが抱える「二つの自己実現」のジレンマ
- 東ゆうが本当に向き合うべきは…
- 「私が欲しかったものは、もう手に入っていたんだ」ものの傑作
鑑賞後の短評
あらすじ
アイドルになることを夢見る高校1年生の少女、東ゆう(演:結川あさき)は。東西南北の美少女を集めアイドルユニットを結成することを目標に動き出し、南の華鳥蘭子(演:上田麗奈) 西の大河くるみ(演:羊宮妃那) 北の亀井美嘉(演:相川遥花)と順調に仲間を増やしていく。ボランティア活動や文化祭を通じて関わりを深めていく四人だが。アイドルとしてデビューし忙しさが増すごとに、ゆうと3人との決定的な価値観のズレが明らかになっていき、ゆうは自身の夢や仲間と、再び向き合うことを余儀なくされる。これからするのは映画批評ではなく…
私はクオリティはともかく、客観的な批評を目指していた。情報を精査し、描写と照らし合わせ、作り手のクセや作家生を分析し、批評する。それが私の目指すべき批評のあり方であり、尊敬する先人たちが行ってきたことだ。だが今作『トラペジウム』に関しては、情動的な評にならざるを得ない。それほどに、私は東ゆうという少女に思い入れてしまったのだ。今後、東ゆうの内心を過剰に決めつけたり、東ゆうの立場に立った文章が頻発するかもしれないがご容赦いただきたい。ここから始まるのは映画批評ではない、自分語りだ。
東ゆうは共感できない主人公か?
さて、公開前からの評判として「主人公には共感できない」という感想がそこかしこらで散見された。これは半分YESで、半分NOだと私は思う。本作は東ゆうに共感できないのではなく、あえて反感を持たせるような作り方を徹底しているのだ。
その理由を、描写を通じて読み解いていきたい。まず私が注目したいのは、視覚的な演出だ。特に重要なパートが含まれる冒頭映像を公式が無料公開しているので、こちらの方を引用しながらお話していきたい。(こちらにリンクを掲載するのが難しそうなため、各人で検索し動画を用意していただけると助かる)
この動画では、映画冒頭にあたる東ゆうが「東西南北」ユニット構想ノートを眺めながら電車に揺られ、そこから降りるシーンと。それに続くように挿入される「なんもない」(歌唱:星街すいせい)に合わせたオープニングアニメーションまでのシーンが切り抜かれている。特に私が注目したいのは、ここでのキャラクターの進行方向だ。東ゆうは最初電車に揺られながら、画面の左の方へと動いていく。そして電車を降りてからもなお焦るように画面左側へと進んでいくのだ。この映画は全体を通して、東ゆうが画面左側へと歩いていくシーンが多い。意地悪にも、他のエキストラが右へと歩いていくのを追い抜くような形でだ。対して、東ゆうの初期衝動が凝縮されたオープニングでは、ゆうは徹底して右側へと進む。星街すいせいのアップテンポな曲調と相まって作中でも屈指の明るいシーンとしてあるオープニングは、右=正道という認識を無意識のうちに観客に埋め込み。左へと歩む東ゆうを不安定な存在として捉える効果を持つ。(そんなゆうが次に右側に向かって走り出すのはいつか、ということを考えると示唆的だ)。
もう一つが、光と影の演出だ。「初めてアイドルを見たときに気づいたんだ、人間って光るんだって」ゆうが時おり強く語る、アイドルとなるべき動機の一言だが。今作は残酷にも、そんな光に憧れるゆうをこそ影に閉じ込める。この映画よく見ると、他のキャラクターに光が当たっているシーンで、ゆうは影にいるという構図が印象的に用いられているのだ。(そんなゆうが光を浴びる=輝く瞬間はいつかというのを考えると今作のテーマが見えてくるが、それは後述する)
上記のように、今作ではあらゆる方法を用いて東ゆうの不安定さを批評的に描く。構造自体が、キャラクターから距離をとって批判しているものなのだから「共感できない」というのも当たり前だろう。だが、そこでキャラクターへの理解を止めてしまうのももったいないと感じるのだ。
東ゆうが抱える「二つの自己実現」のジレンマ
では、なぜゆえ東ゆうは不安定で、かつ正道から外れた方向へと歩いていってしまうのか?私が思うに、彼女は「アイドルになる」という目標の中で、実は同根ではない二つの問題を同時に解決しようとしてしまっているのだ。ゆうが抱える二つの問題とはなんだろう? 一つは極めて純粋な初期衝動だ。星街すいせいの歌に乗せて語られた、ゆう自身のアイドルに救われたという経験。全体的に暗く赤っぽい画面の中、テレビの中のアイドルだけが輝いていたのが印象的だった場面だ。その時アイドルが持つ光に打たれたゆうは、自身もその光へ近づこうとアイドルを志し始める。「初めてアイドルを見たとき思ったの、人間って光るんだって」というセリフは彼女が持つ憧れを端的に表したもので、それを動機にアイドルを目指していくという本作はここだけ取れば王道の成長ものだ。
だが、彼女はもう一つ大きな問題を抱えている。それは彼女自身の実存的感覚の欠如、言い換えれば他者に対する鬱憤と不信感だ。彼女は同スタジオ制作の代表作『ぼっち・ざ・ろっく』の後藤ひとりとはまた違った意味でコミュニケーションに対する不全感を抱えている。身も蓋もない言い方をすれば「コミュ障」なのだ。現に、彼女はクラスの中でも浮いていて。クラスメイトからも悪口をよく言われているという描写もある。その理由は明らか、東ゆうは圧倒的に空気が読めない。その上言葉に棘があり、共感性が低い。正直、クラスにいたら嫌われるのも納得ではある。今作が「主人公に共感できない」という感想を持たれる一因として、主人公の強引さと、他者に対しての共感性のなさが挙げられる。それは裏返せば、他者に対する苦手意識とそれに付随する憎悪を育むものともなってしまっているのではないだろうか。だから彼女はあえて他者に対するプライオリティを下げて接する。「自分の自己実現の道具」として見ることによって、離れていった時の心痛のリスクをコントロールしているのではないだろうか?
東ゆうが本当に向き合うべきは…
「アイドルとして輝きを手にしたい」「他者に対する鬱憤と不信感を塗り替え、自分の人生を潤いあるものにしたい」この二つの全く異なる目標は。東ゆうの中で「自分が生きる意味を獲得するための自己実現」という理屈に統合され限りなくごっちゃにされていく。だから彼女にとって「アイドルを目指す」ということは究極の自己実現なのだ。ユニット東西南北の他のキャラクターは、アイドル活動を通さずとも自分の生きる意味を確立できるキャラクターだ。大河くるみはロボット工学、亀井美嘉は恋愛、華鳥蘭子は生きる意味という小さなスケールで生きる人間ではないことが明かされる。彼女たちはアイドル活動を通さずとも実存的感覚を確立できているし、むしろアイドル活動は彼女たちの生きる意味を奪っていく。主人公の東ゆうだけが「アイドルを目指す」ということをやめてしまえば空っぽの人間になってしまうのだ。
前述した通り、東ゆうの問題は「アイドルを目指すのをやめれば自分には何もない」という自己認識と現実にある。だが、本当にそうだろうか。映画ラストに明かされる「トラぺジウム」のタイトル回収にもなるワンシーン。この写真こそが、彼女の生きる意味に他ならない。「友達」と笑い合い、演技ではない満面の笑顔を見せる瞬間。この瞬間が作れる居場所こそが、ゆうが本当に求めていた何かだった。それは他の3人も同じだったのではないだろうか。ゆうは他の三人を自分の都合のいいように利用し、生きる意味を奪い、ひどいこともたくさん言った。だが、それ以上に特別な時間を過していたというのも真実ではないか。
ラスト近く、ゆうは美嘉に尋ねる。「私まだ釈然としないんだけど、恋愛ってそんなに大事?」背景のわりに重い感じもなく交わされるセリフだが、これはゆうにとって非常に重要な問いかけだ。「利益や損得を超えて他者と交流することに生きる意味をなぜ見出せるの?」という、彼女が向き合うべき最大の問題に対する答えを求めるものだからだ。私が連想したのは映画『桐島、部活やめるってよ』のラスト、前田(演:神木隆之介)に宏樹(演:東出昌大)が問いかけるシーンだ。「将来はどうするんですか?映画監督ですか?女優と結婚ですか?」これも冗談めかしたやりとりの中に宏樹の実存的葛藤が込められていたが。本作でも同様だと思う。そんな問いに対し、美嘉は優しく応える。「そうだね、大切な人ができたら。わかると思うよ。」
時系列は未来へと飛ぶ。それぞれが自身の人生を歩み、大人になった姿で4人は再会する。その時に見る写真こそ美嘉のセリフと呼応するような「大切な誰かと一緒にいることで満たされている自分自身」の姿だった。ゆうは気づく、アイドルになることではなくても、こういった形で私は満たされていたのだと。写真の中で、彼女は輝いていた。「トラペジウム」不等辺四角形という意味で本作では使われてきた言葉が。輝きを放つ星という意味に反転する。本作はアイドルを目指していなかったら空っぽだった少女が、アイドルを目指していなくても満たされる少女へと成長する物語だったのだ。
「私が欲しかったものは、もう手に入っていたんだ」ものの傑作
本作、非常にややこしい構成となっているのでわかりずらいが。私は「あっ、私が欲しかったものは、もう手に入っていたんだ」ものの映画だと思う。つまり目標に向かって邁進していく過程で、大切なのは目標そのものではなかったということに気づく作品だと思ったのだ。とは言っても、この文章は私の解釈、私の考えた『トラペジウム』像でしかない。見たひと全てがこの映画から何かを感じ、キャラクターに感情を動かされてしまう。100人が見れば100人が違う感想を持つという点に置いて、本作はまさしく「カルト映画」の素養を持ち得た傑作と言えよう。
客観的に見ても『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』や『勝手にふるえてろ』等の実存的不安を描いた傑作に引けを取らない一作だと思うので。ぜひ劇場での鑑賞をおすすめしたい。
(2024/5/10 公開作品)