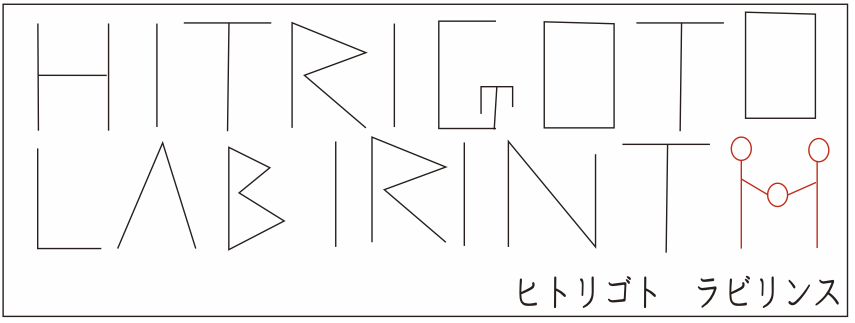2024・3/29(金)に公開されたクリストファー・ノーラン最新作となる映画『オッペンハイマー』。原子爆弾の開発者を描くというセンシティブな内容から、日本では公開前から議論が絶えなかった。公開されて以降はさらに話題を呼び、さまざまな人がさまざまな角度から感想を述べる話題作となっていった。そんな『オッペンハイマー』を私はどう見たのか、語ります。
目次
あらすじ
原爆の父と呼ばれたロバート・オッペンハイマー(演:キリアン・マーフィー)。マンハッタン計画を主導し、トリニティ実験を成功させながら晩年は原子爆弾に対し否定的な立場を取った彼は、何を思い原爆開発に心血を注いだのか。原子力委員会委員長ルイス・ストローズ(演:ロバート・ダウニー・Jr)との対立、共産主義者であるかを精査する公聴会での模様を通して彼の人生を追憶する伝記映画。第96回米国アカデミー賞作品賞受賞。
https://www.oppenheimermovie.jp/# 映画公式サイト
オッペンハイマーのキャラクター造形
・自分という他者にコントロールされるオッペンハイマー
オッペンハイマーの人物像は、冒頭にあるリンゴを巡るやりとりに集約されているといってもいい。実験が苦手だった彼は、教授からの厳しい叱責に耐えかねて教授の机にあったリンゴに青酸カリを注入する。だが、その後後悔に苛まれ、教授が口にしようとしていたリンゴを奪い取り、自らゴミ箱へと放り込む。このリンゴが終盤作られる原子爆弾と対になっていることも含め映画全体にとって非常に重要なシークエンスだ。彼は常に、自身の決断を後悔し結果に対する苦悩を抱えている人間だということが示されるからだ。このキャラクター像を、これまでのノーラン作品が描いてきた主人公像と比較すると面白い。
・「自発的な選択」ができない不幸を抱えて
https://katojunichiculture1991.doorblog.jp/archives/4928217.htm
上記のURNは『フォロウイング』と『テネット』の比較を通じて、ノーラン映画における主人公像について語った私の旧ブログのリンクだ。ここでも語っているように、ノーラン映画の主人公は常に何者かからコントロールされ、自発的な行動を取れない存在だ。その意味で言うとオッペンハイマーという存在は自分で自分をコントロールできない男だ。自分という他者にコントロール権を握られた男と言い換えてもいいだろう。それ故に彼は、常に行動の結果に対し後悔と苦悩を抱え続ける。選択の帰路に際し、どちらかを選択した時点で詰んでいる人物なのだ。今作におけるオッペンハイマーは共感不可能な人物として受け止められることが多いが、それも当然だろう。オッペンハイマー自身が、自分のことがわかっていないのだから。むしろ、自分で自分をコントロールできない存在という点で、個人的には思い入れるキャラクターだった。『テネット』や『ダークナイト』では他者にコントロールされた世界の呪縛を離れ、自発的な選択をすることをカタルシスにしてきたが。『オッペンハイマー』では何を選択しても彼は不幸になる。この独特のキャラクター設定が、後述する本作の絶望感に拍車をかける。
歪なまでにアンチカタルシスな構成と作劇
今作は下記2点のような理由から、カタルシスが生まれづらく。どこかにカタルシスを置きづらい、カタルシスを意図的に排した構成になっている。
原子爆弾というセンシティブなテーマ設定
ヒロシマ、ナガサキといった民間居住地にも投下され、世界を核戦争の恐怖へと陥れた原子爆弾。その事実を重く受け止めれば受け止めるほどに、原爆開発秘話たるオッペンハイマーの伝記を明るいものとして描くことは憚られる。事実、本作でも作中でカタルシス溢れるシーンとして描かれるべきシーンはことごとく相対化されるのだ。例えば、トリニティ実験の成功に沸く研究者たちというシーン。普通なら主人公が先導する巨大プロジェクトの成功は物語の大きなカタルシスとなり得る。だが、本作はそう描かない。当該シーンをオッペンハイマーが苦悩するシーンで挟むことによって、熱狂的な盛り上がりを逆に歪なものへと変えてしまう。つまり本作は、プロジェクトX的なお仕事ものでは盛り上がるシーンをあえて相対化し、意識的にカタルシスを排した作劇へと作り替えたのだ。
題材認知度が高い
トリニティ実験やマンハッタン計画がどういう道のりをたどりどのような影響を世界に与えたのか。それを全く知らずに今作を鑑賞する人は少ないだろう。それ故に、実験が成功するのか・しないのかといった手前の部分にハラハラドキドキをおけない。むしろ「彼が世界を変えてしまった」というキャッチコピーにも、むしろ成功は前提という雰囲気すら感じる。つまり、映画の筋書き自体は全員がわかった状態で鑑賞することになる。こんなの、手札を晒して大富豪をするようなものだ。
ノーランはこのアンチカタルシスさをどう捌いたか
オッペンハイマーは題材の特性上、手品の種を全て明かした上でその盛り上がりすら相対化してみせた歪な作品となることを余儀なくされた。だが、凡百の監督が撮ればただ盛り上がりに欠けるような映画になりかねない本作も。ノーランは手練手管を駆使し、極上のエンターテインメントにしてみせる。
ストローズとの対立とその勝利を取り急ぎのカタルシスとして提示する
今作の第二の主役とも言える、原子力委員会のストローズ。彼はオッペンハイマーを妬み彼を攻撃するキャラクターとして設定されている。オッペンハイマーから見た視点の物語に絞って作品が構成されている本作では、ストローズは純然たる悪役だ。またフラットに見ても極端な思想を持つ(映画内でそう描かれているだけかもしれないが)ストローズはオッペンハイマーと同じくらい思いいれるのが難しい人物でもある。そんな彼が審問会で(間接的に)オッペンハイマーに敗北する様子は痛烈に見えるし、それを痛烈に描くことは倫理的にもOKだ。この対決を一応のゴールとすることでオッペンハイマー勝利のストーリーをとりあえずは作ることができる。
とてつもなく豪華な俳優たちのアンサンブル
今作は映画のどのシーンを切り取っても、ベテラン役者や勢いある若手スターが画面に大集合しており。その演技のアンサンブルを見ているだけでも華がある。『ナイトメア・アリー』という作品を撮影した時、監督のギレルモ・デル・トロが「これはスターという怪獣が揃い踏みする怪獣映画なんだ」と自作を語ったが、そういう意味では『オッペンハイマー』も「怪獣揃い踏みの怪獣映画」だろう。何より主演のキリアン・マーフィーが素晴らしい。少しバランスを間違えば感じが悪かったり、過剰に人間的なキャラクターになってしまうところを絶妙なバランスで「孤高の天才科学者」を演じきった。本作の成功は彼ありきのものだと思うし、アカデミー賞主演男優賞も納得だ。
映画というものが持つプリミティブな面白さ
映画は、ストーリーを語るものであるが。同時にそれを超えて観客の心を揺さぶる力を持ったものだ。私はジャン・リュック・ゴダールの死後公開された怪作『遺言/奇妙な戦争』を見た時そう思った。『遺言/奇妙な戦争』はゴダールの実現しなかったストーリーボードを羅列する形で映画化したもので、ストーリーラインは全く存在しない。だがストーリーボードを提示していくシークエンスの中に巧みに音を入れ込むことで、観客の心を揺さぶる。音と光を人間が受け取る時のプリミティブな生理反応こそが、映画の本質であるとゴダールは知っているからだ。そして、それはノーランも同じではないだろうか。本作、全編にわたってうるさいくらい音がずっと鳴っている。映画において音こそが観客の心を揺さぶるものだとノーランはわかっているからだ。トリニティ実験のシーンをこんなにもサスペンスフルなものにしているのも音のマジックだ。ノーランはこれまでも「よくわからないけど面白い」という映画をずっと撮ってきた監督だ。ノーランの映画はなぜ面白いのか。それは上記の映画の本質に誰よりも敏感で、それ故にうまく扱えたからというのは褒めすぎだろうか。
ノーランという巨匠だからこその映画
何より、その全てを達成しうる監督クリストファー・ノーランという巨匠に拍手を送りたい。自身のブランドを駆使し、求めるビジョンを実現させ、それでさらなる評価を得てみせる。戦略家にして作家、異端の奇才クリストファー・ノーラン。『オッペンハイマー』という題材を仕上げるにあたって彼以上の適任はいなかったと思うし、本作はノーラン映画の集大成であり、これまでのフィルモグラフィーは今作のためにあったのではと思わせる一作だ。