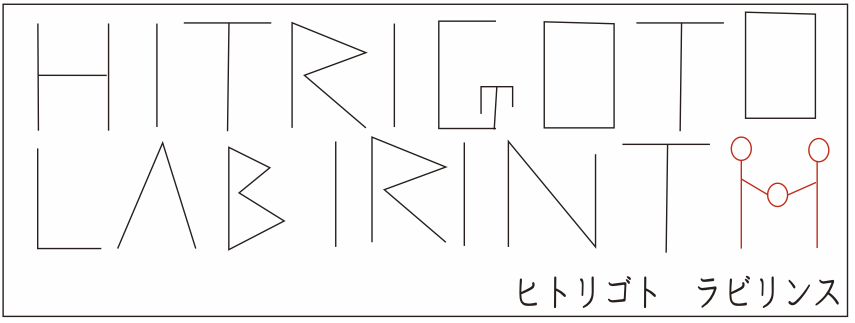ドライブ・マイ・カー』は濱口竜介氏によって監督され、アカデミー賞含め世界的に高く評価された。日本映画としては初の作品賞ノミネートをはじめ監督賞、脚色賞など四部門でノミネートされ、日本映画としては13年ぶりとなる外国語映画賞を受賞した。村上春樹:著『女のいない男たち』の中に収録された同題名の短編を原作としており、世界的に評価が高い村上春樹作品の映像化ということも注目が集まった一因として挙げられている。
本作を読み解く上で重要になるのが、作品の中で展開される「演技」というものの扱い方だ。劇団が舞台である以上演技が重要なのはあたり前ではと思われる方も多いだろうが、私が言いたいのはそういう直接的な意味での演技ではない。
ほとんどの主要登場人物が、自分の本音をつつみ隠す演技を絶えずしているということだ。
ドライブ・マイ・カーと同監督作品である『偶然と想像』を、ライムスター宇多丸氏が評した際に使った表現がドンピシャだったので引用させて頂く。
「一見するとリアルに(ウェルメイドに)見えるシーンこそがまさに本音を押し殺した演技をしている瞬間であり、逆に現実とは遊離したトーンで会話しているシークエンスこそが登場人物にとってはリアルな心情を吐露している状態なのである。」これは、ドライブ・マイ・カーでも全く同じことが言える、登場するすべてのキャラクターが大なり小なり何かを隠している人たちだからだ。だからこそ単に日常会話に見えるシーンがとてもサスペンスフルなものとして提示される。いつ抱えた「本音」が破裂するとも分からないからだ。
逆に本音の部分は、抽象的にも見える「演技」によって語られる。家福と音の性交渉が行われるシーンの後。ここで音は、ヤツメウナギの物語を語る。非常に寓話的で本意はつかみずらい。しかし、音はこの物語の中で「禁じられた不貞を働いていること」を告白し、「それが発覚し、やっと辞められる(のか?)」というところで締めている(少なくとも、この時点では)。ヤツメウナギというメタファーを考えても、物語を通して彼女が自分自身の現状を告白していることは明白だろう。
そして演技の中にこそ本質があるというのは、主人公である家福も同様である。彼は車内で『ワーニャ伯父さん』を朗読する、その朗読の内容こそが実は何よりも雄弁に彼の本音を語っている。何ならラストに吐露するような心情に近いことを、朗読を通して言っていたりもするくらいだ。
だから彼は、『ワーニャ伯父さん』で主演をすることができない。それは彼が一番恐れている自分の本音や現実と向き合うという行為だからだ。
「自覚している本音(もしくは現実)と向き合うことを恐れる」キャラクターは、実は日本のカルチャーで今よく描かれるモチーフでもある。記憶に新しいのはやはり『すずめの戸締まり』だ。主人公の岩戸鈴芽はある欠落を抱えたキャラクターであり、その欠落の本質を自覚しながらも「閉ざして」しまったキャラクターとして描かれる。『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に登場する雉野つよしも、そういったキャラクターの内の一人であろう。妻以外に生きる理由を持たない彼が激動の展開の中それに否応なく気付かされ、その中で変化・成長していく姿は『ドンブラ』の大きな見せ場だった。私の趣味に寄せて書かせて頂くなら、『宇宙よりも遠い場所』というアニメーション作品は『ドライブ・マイ・カー』に近いテーマ性と成長のプロセスを取った作品だったと思う。他にも多数のカルチャーの中でそういったキャラクターが多く描かれているし、ヒットする作品ではこの要素が含まれるものも多い。
その乗り越え方も作品によってさまざまだが、本作『ドライブ・マイ・カー』においては自分でない他者にハンドルを託すということが救いに繋がっている。家福は他者に車を運転されるということを過剰に嫌がる、それは「自分の人生の舵取りを他者に任せられない。」という比喩でもある。これは私の想像だが、そうすることによって自分の向き合えない部分、つまり本音や現実の部分が否応なく照射されてしまうことを恐れているからではないだろうか。だが家福は、他者にハンドルを託すという行為を通じてむしろ隠しておきたい本音の部分を共有できる他者と出会い、音に会えないという現実をこそ生きる力を得る。『ワーニャ伯父さん』のラストシーンが映画では描かれるが、その演技を通して禍福が体験するのは「受容」だ。自分の本音を感情のまま語っても、それを受け入れてくれる他者はいるとこの映画は語る。そうだ、自分の自我が崩壊した瞬間があったとして、その瞬間、自分を肯定してくれるのは他者以外にいないのだ。
そしてそれこそが、世界的評価の大きな一因ともなっているのではないかと思う。アカデミー賞含め世界の潮流はダイバーシティ、多様性だ。そしてそれは自己の受容からこそ始まる。その自己の受容を描いた物語だからこそこんなにも胸を打ち、世界的にも評価されたのだろう。そして奇しくも今年アカデミー賞を受賞した『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』はアジア系の俳優がメイン所を占める「受容」の映画だった。
最後に、個人的な話になるが「自分の気持ちを伝えることを、もしくは理解することを怖がった結果、もう取り返しのつかないことになる」という体験は、幾度となく繰り返してきた。そんな私にとっても、突き刺さる作品となった。