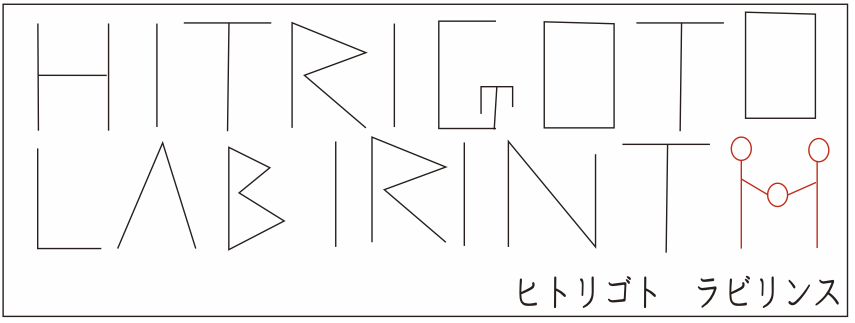私が大学で連載しているフリーペーパー『HITORIGOTO LABIRINTH 』の本文内容を、こちらのブログを借りて掲載させて頂きます。
目次
- リム・カーワイ監督作品のドキュメンタリー映画『ディス・マジック・モーメント』について
- 『ディス・マジック・モーメント』シネマスコーレ上映後舞台挨拶について
- 映画問わず語り『悪は存在しない』(濱口竜介 監督作品)
リム・カーワイ監督作品のドキュメンタリー映画『ディス・マジック・モーメント』について
映画『ディス・マジック・モーメント』は深く胸に染み入る傑作だ。映画に切り取られることで、初めて観測される瞬間をとてもソリッドに映し取る。
本作の魅力を語る前に、まず「映画」というものがいかにドキュメンタリックな芸術であるかを語らねばならない。例えば、シルヴェスタ・スタローンの出世作となった『ロッキー』。『ロッキー』見た観客は売れずに燻る主人公ボクサーを同じ境遇にある俳優スタローンと重ねた。ロッキーが映画内で勝ち得る栄光は、そのままシルヴェスタ・スタローンの成功に間違いなかった。
『第三の男』もまた、映画が持つドキュメンタリックさを自覚的に打ち出した作品だ。フィルム・ノワールの代表として出されることが多い本作だが。他のフィルムノワールと一線を画している要因として。第二次世界大戦終了直後のウィーンで撮影されたということが挙げられる。戦争で破壊されたウィーンの都市が画面内に残るからこそ、本作で描かれる戦争で心を喪った登場人物たちの葛藤がより深いものとして提示されるのだ。
すべからく映画というものは撮影された当時の時代性を反映し、その土地の記憶と演じた役者の記憶、その全てを内包していく。
そして映画『ディス・マジック・モーメント』が生み出す感動も、そういった映画の特性に起因するものだ。『ディス・マジック・モーメント』は『ロッキー』のようなアメリカン・ドリームを体現するようなドラマも、『第三の男』のようなサスペンスフルなクリフハンガーも持たない。しかし、映画というメディアが持つドキュメンタリックな性質によって強烈な感動を呼び起こす。
監督は、自身と支配人の対談を通し映画館の歴史を解き明かしていく様子を、落ち着いたトーンで切り取る。定点カメラで捉えられる、ミニシアターの座席に座って「二人が喋ってる」様子。この日常こそを特別だと思えるのは、映画構成の力が大きい。冒頭に提示される監督が今作を撮影するきっかけにもなった、テアトル梅田の閉館。大阪でも由緒あるミニシアターの閉館は、監督にショックを与える。今池シネマテークの一時閉館を経験した私たちにとっても他人事ではない感情だ。監督が訪れるミニシアターも、否応なく変化する。小倉昭和館という劇場は火災で全焼し、首里劇場の金城館長は逝去。愛する映画館が愛する形で残されることの難しさを、これでもかと突きつける。
だからこそ、今の姿がフィルムに残り続けるということは何よりも尊いということをこの映画は提示するのだ。「首里劇場で上映する」という形で引用される監督の前作『あなたの微笑み』のワンシーンでは、金城館長が生き生きと演技をし、カンフーポーズを披露する姿が映し出される。この映画の中では金城館長は永遠なのだ。映画が時間を閉じ込めるという事実が、これほどまでに嬉しかったことがあっただろうか。私は感動した、これまで見てきたどんな作品よりも。映画に残す意味と意志を感じたからだ。
リム・カーワイ監督は、映画というドキュメンタリックなメディアを使って。訪れた22館のミニシアターを「永遠」にしてみせた。その目撃者となり、永遠の一端をになえたことが観客としてとても誇らしく、また感動的だった。
『ディス・マジック・モーメント』シネマスコーレ上映後舞台挨拶について
私は映画『ディス・マジック・モーメント』を、名古屋のミニシアター「シネマスコーレ」にて鑑賞した。シネマスコーレは映画監督の若松孝二が1983年に立ち上げたミニシアターで、「映画の学校」をコンセプトに独自のチョイスで作品を上映し続けている。名古屋駅から徒歩5分の立地にある素晴らしい映画館だが。なんと、今作『ディス・マジック・モーメント』でも取り上げられているのだ。観客席に座って対談する映像を、同じ観客席に座りながら見ているという。得難い体験をすることができる。
5/25の上映後には、舞台挨拶トークショーも開催された。木全純治代表・坪井篤史支配人・リム・カーワイ監督が登壇し、映画について闊達なトークを繰り広げた。特にシネマスコーレで撮影が行われた背景として「帰り道に近かったから」という言葉が冗談めかして飛び出したのはとても面白かった。そして監督は、この作品を撮るに当たっての矜持も語る。「コロナ禍におけるミニシアターの現状のようなものは、あえてカットした。コロナ禍でミニシアターが苦しいのはみんな知っているから。それよりもミニシアターやその支配人がどういう道のりを歩んで今運営されているのかということを描きたかった。」この信条があるからこそ『ディス・マジック・モーメント』という作品が持つ特別な空気感が出来上がったのではないかと、私は思う。今作は「映画館」という施設が持つ物語を捉え、それを永遠へと昇華するものだからだ。
そんなリム・カーワイ監督だが。2024年6月29日にまた新作『すべて、至るところにある』がシネマスコーレにて公開される。東京のイメージフォーラム等ですでに公開されていたものの、名古屋での公開は初となる。『すべて、至るところにある』は旧ユーゴスラビアのバルカン半島を舞台とした映画で「バルカン半島三部作」の完結編となる。バルカン半島の雄大な自然をベースに、コロナ禍や戦争といった現代の問題を撃つSF抒情詩となっているそうだ。6/30には監督の舞台挨拶も開催されるので、ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。
(2024/1/27 公開作品・名古屋では6/29よりシネマスコーレで公開)
映画問わず語り『悪は存在しない』(濱口竜介 監督作品)
(2024/4/26 公開作品)
まず大前提として本作は「あまり情報を入れずに見た方が面白い」タイプの作品だ。まだ未見だったら、まっさらの状態でぜひ映画館で見てほしい。
濱口竜介と聞くと、非常に文学的で難解な作品を意識される方も多いのではないだろうか。それは半分正解で、半分は間違いだ。濱口監督は、アート映画的な文学性を持ちながら。俗っぽい人間の感覚やストレートなエンタメ性を取り入れた「普通に面白い」映画を作る監督である。
本作も、それは同様だ。本作は山奥の集落で暮らす巧の視点で幕を開ける。彼らの暮らす町は雄大な自然と美しい水をアイデンティティにしており、住民もそこに誇りを持っている。だが、そんな街にグランピング場を建設しようと試みる企業・プレイモードがやってくるのだ。第一幕はプレイモードと住民との衝突を描く。特に説明会のシーンは大きな見せ場と言えよう。プレイモードが提出する穴だらけの計画に、住民がツッコミを入れていく。非常に痛快なシーンだが、その中で巧の一言が異彩を放つ「僕は開拓には賛成派だ、僕らだって自然に影響を与えてきた、大事なのはバランスだ」実際、本作において集落の住民もパーフェクトな存在としては描かれない。何度もアップになる子鹿の死体や、所々に挿入される煙・ガスの描写がその証左だろう。住民もどこかで、自然に対して「悪」の部分を持つのだ。
そんなシークエンスが終わると、映画の視点は反転する。第二幕、舞台は東京・プレイモードの会議室へと移るのだ。ここでは、第一幕では「悪」役だったプレイモード社員の方に思い入れてしまう。計画の杜撰さに気づきながら、中間管理職として職務を全うしなければならないという彼らの板挟み感。そして濱口マジックによって何倍にも魅力的に見えてしまう車内での会話シーン。社員にも彼らなりの事情があるのだと、説明を超えた描写で提示する。
そして、彼らはまた集落を訪れる。だが、今回は前回とは違う。住民に対し、少なくとも敬意を持った対応をしようと心がける。明確な「悪」などいない、それぞれの事情が重なった時に。折りあえぬ何かが出てくるだけなのだ。そんな優しい結論に着地するのかと思いきや、映画は思わぬ方向へと急加速する。
自然というのはあくまでシステムであり「美しい」や「過酷」と言った解釈を与えることは、人間的な摂理に自然を落とし込んでいるだけにすぎない。「悪」も同じなのだろう、人間の生というシステムを個人や団体と言った視点の益に落とし込もうとするから「悪」が生まれるのだと、この映画は告げているのではないだろうか。自然や人間というシステムはもっと理解不能で、個人の視点では決してその全容をつかむことはできないのだ。この映画は、まさにそれを象徴するような幕切れをみせる。非常に解釈の開かれたラストではあるが。一つ言えるのはこの映画は自然を美しくも、過酷にも切り取っていないということだ。今作のファーストカットは、木々の枝を長回しで捉えたものだった。この捉え方が、今作のテーマを象徴している。